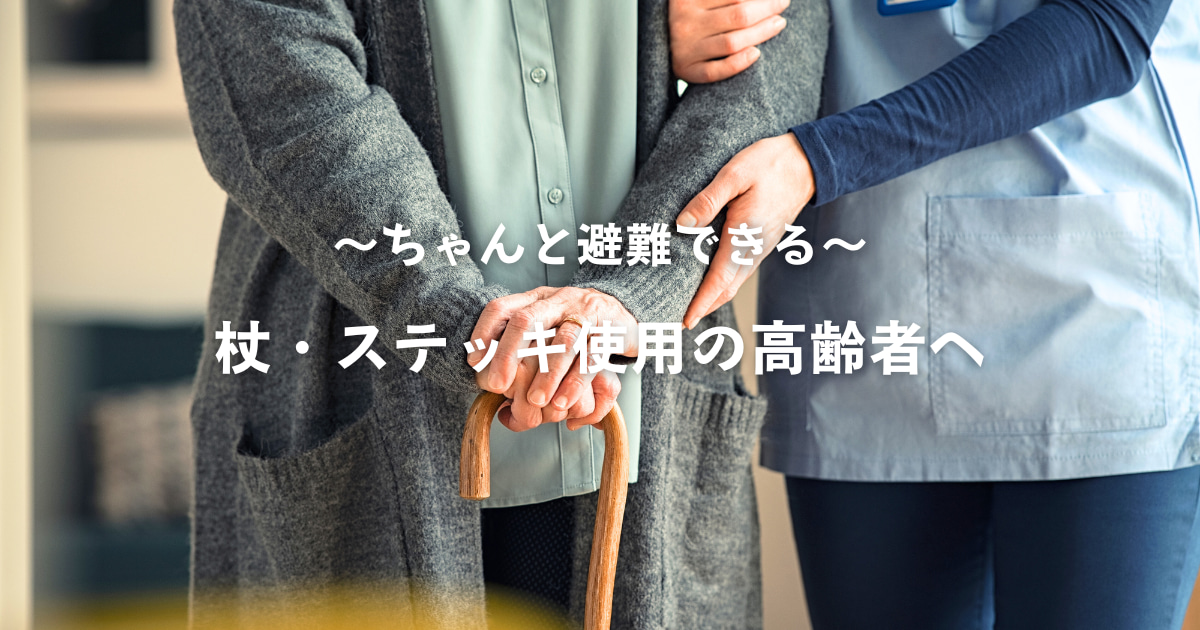「杖やステッキを使っていると、災害時にちゃんと避難できるか不安…」
そんな心配をお持ちの方や、ご家族の方は少なくありません。実際、災害時は避難所までの移動や、慣れない場所での生活が大きな負担になります。
ですが、あらかじめ備えておくことで、その不安を少しでも和らげることができます。
今回は、杖・ステッキを使う高齢者やそのご家族向けに、災害時の防災対策をお伝えします。
*名古屋市では、高齢者のために「防災安心まちづくり運動」に取り組んでいます。
杖・ステッキ使用時に注意したい災害リスク

杖やステッキは、歩行を助けてくれる大切な道具ですが、災害時には思わぬ危険につながることもあります。事前にリスクを知っておくことで、備え方や心構えが変わってきます。
転倒・ケガのリスクが高まる
地震や台風の際、突然の揺れや強風、足元の悪さで、杖をついている方はバランスを崩しやすくなります。特に以下のような場面は要注意です。
・地震直後のガタガタした床や、物が散乱した室内
・大雨・洪水の後のぬかるんだ道や水たまり
・強風時、杖をつく手元がふらつきやすくなる
ご自宅の床を滑りにくくするマットを敷く、段差の対策をしておくことも大切です。
避難経路での困難
いざ避難となった時、以下のような障害があると、杖やステッキ使用者にとって大きな負担になります。
・エレベーターが停止し、階段しか使えない
・狭い通路や段差が多い避難ルート
・地面がぬれていて滑りやすい
事前に避難ルートを家族と一緒に確認しておくと、いざという時も安心です。
避難所内での移動や生活のしづらさ
避難所では、多くの人が集まるため、以下のような困りごとが起きがちです。
・混雑していて杖をついて歩きにくい
・床が固く、長時間座るのがつらい
・荷物置き場やトイレまでの移動が大変
簡易イスや滑り止め、目印グッズを用意しておくと、少しでも快適に過ごせます。
周囲のスピードに焦ってしまう
災害時、周囲が慌ただしく動くことで、「自分も早くしなきゃ」と焦り、かえって転倒やケガにつながることがあります。無理に合わせようとせず、「私は私のペースで」と落ち着いて行動することが大切です。
こうしたリスクを知っておくことで、ふだんの備えや家族・地域との連携が、より具体的になります。「どうせ私には無理…」とあきらめず、小さな工夫から始めていきましょう。
災害時のために今できる備え

杖やステッキを使っていると、「もしも災害が起きたら、ちゃんと避難できるかな…」と不安に感じる方も多いと思います。ですが、日頃からできるちょっとした準備を積み重ねることで、その不安をぐっと減らすことができます。
ここでは、【自宅の工夫】と【持ち出しの備え】に分けて、具体的な対策をご紹介します。
自宅の安全を整える
ふだんの暮らしの中で、ちょっとした工夫をするだけで、災害時の危険を減らすことができます。
✅ 家具の転倒防止
背の高い棚やタンスには転倒防止器具を取り付け、万が一の地震でも安全を確保。
✅ 滑りにくい床づくり
玄関や廊下、よく通る場所には滑り止めマットやカーペットを敷くと安心。特に夜間や地震直後は、床が散らかりやすくなるので備えておきましょう。
✅ 段差の解消やスロープの設置
ご自宅に小さな段差がある場合は、簡易スロープや手すりを設置。
✅ 杖やステッキの置き場所を決めておく
玄関や寝室、リビングなど、すぐに手が届く場所に常に置いておきましょう。地震の揺れで物が散乱しても、探し回らずに済みます。
非常持ち出し袋を自分仕様にする
防災用の非常持ち出し袋も、杖やステッキを使う方に合わせた工夫が必要です。
✅ 杖やステッキの予備・替えパーツの準備
万が一、災害時に杖が壊れてしまったり、先ゴムが取れてしまった場合に備えて、軽量タイプの予備や交換パーツを用意しましょう。折りたたみ式だと持ち運びも楽です。
✅ 軽くて背負いやすいリュック選び
片手がふさがる分、リュックは軽量で身体にフィットするものがおすすめ。背負いやすさは必ず確認しましょう。
✅ 必要なお薬と健康情報カード
持病や必要な薬、かかりつけ医の情報を書いたカードを、非常袋に入れておくと安心。普段飲んでいる薬の1~2日分も準備しておきましょう。
✅ 休憩できるグッズの準備
簡易イスや折りたたみマット、滑り止めシートがあると、避難所や移動時も休憩しやすくなります。
家族や地域とつながっておく
一人でがんばるのではなく、家族や地域と協力し合うことも大切な備えです。
✅ 避難先・連絡方法の確認
ご家族と避難場所や集合場所、連絡方法を決めておきましょう。特にスマホが使えない時のために、紙のメモも用意しておくと安心。
✅ 近所の方への声かけ
普段から顔を合わせておくと、「もしものとき助けてもらえる」「自分も誰かを助けられる」関係が築けます。
✅ 地域の防災訓練に参加する
実際に避難ルートを歩いてみたり、避難所の場所を知っておくと、いざという時も落ち着いて行動できます。
杖・ステッキユーザー向けおすすめ防災グッズ

杖やステッキを使っていると、いざという時「移動が心配…」「避難所で困らないかな…」と不安に感じます。でも、事前に少し工夫して必要な防災グッズを準備しておけば、いざという時も安心して行動できます。
持ち出し用・避難時に役立つアイテム
✅ 折りたたみ式・軽量タイプの予備の杖
災害時、杖が壊れたり、移動中に必要になることも。折りたたみ式なら持ち運びがしやすく、リュックや非常袋に入れておけます。
✅ 杖の先ゴム(替え)
地震や雨などで足元が悪くなると、先ゴムが劣化・破損することも。替えを用意しておくと安心。
✅ 滑り止め付き手袋
避難時や片手で荷物を持つ際、杖のグリップ力を高めるためにも、滑り止め付きの手袋は便利。
✅ 軽量リュック(肩・腰に負担が少ないもの)
両手をなるべく空けられるリュックは必須です。シンプルで軽いものを選びましょう。
✅ 反射材やライト
夜間の避難や停電時に備えて、杖やリュックに反射材や小型ライトをつけておくと安心。
避難所・在宅避難で役立つアイテム
✅ 簡易イス・折りたたみ椅子
長時間立っているのがつらい方に。軽量タイプなら持ち運びも簡単。
✅ 滑り止めマット・シート
床が滑りやすい避難所や仮設トイレ周りでの転倒防止に役立ちます。
✅ 小さなクッション・膝当て
床に座るのがつらい場合や、膝への負担軽減に。普段使いもできるのでおすすめです。
✅ 杖の名札・連絡先タグ
避難所では杖を間違えたり紛失することも。名札や簡単な連絡先をつけておくと安心。
✅ 自分の体調メモ・持病カード
高血圧や糖尿病、服薬内容を書いたカードを用意しておくと、避難所での医療サポートも受けやすくなります。
家の中の安全グッズ
✅ 手すり・滑り止めの設置
玄関やトイレ、廊下など、ふだん使う場所に手すりをつけておくと、災害時の避難もスムーズです。
✅ 家具転倒防止器具
地震時の家具転倒を防ぐだけでなく、室内の安全な歩行スペースを確保できます。
✅ 停電対策のライトや懐中電灯
停電時、暗い中での移動は非常に危険。常に取りやすい場所にライトを用意しておきましょう。
家族・地域とできる「助け合い」の準備

災害時、「一人では不安…」「避難できるか心配…」と感じるのは、誰にとっても自然なことです。特に杖やステッキを使っている高齢の方にとっては、避難やその後の生活に不安を感じやすいものです。
だからこそ、ふだんから家族や地域の方とつながりを持ち、助け合う準備をしておくことが、とても大切なんです。
家族でできること
✅ 避難場所・連絡方法を決めておく
ご家族と一緒に、避難所や集合場所、緊急時の連絡方法(電話・メール・SNSなど)を話し合っておきましょう。紙に書いて、すぐに見える場所に貼っておくのも安心。
✅ 役割分担を決めておく
災害時、誰が何を持つのか、誰が高齢者をサポートするのか、ざっくりでも良いので決めておくと、いざという時も慌てません。
✅ 防災訓練を家族で体験してみる
実際に非常袋を持ってみたり、杖をつきながら避難経路を歩いてみたりすることで、必要な準備が見えてきます。
地域でできること
✅ 近所の人に「ひと声」をかけておく
顔見知りになるだけでも、災害時に「大丈夫?」「手伝うよ」と声をかけてもらいやすくなります。
✅ 「防災マップ」を確認する
お住まいの地域の避難所や危険箇所を事前に把握しておくと、安心感が違います。各都市の公式サイトなどで確認できます。
✅ 地域の防災訓練に参加する
自治会や町内会が実施する防災訓練は、地域の方とつながる絶好の機会です。杖を使っている方も無理のない範囲で、ぜひ一度参加してみてください。
✅ 「災害時要配慮者登録制度」を活用する
名古屋市では、支援が必要な方の情報を登録することで、災害時に地域の協力を得やすくなる制度があります。詳しくは下記の名古屋市公式Webページをご覧ください。
小さな声かけが、大きな安心につながります
助け合いは、特別なことをしなくても大丈夫。普段の「こんにちは」「お元気ですか?」といった、ちょっとした声かけが、災害時の大きな支えになります。
地域でのつながりがあれば、いざという時「助けてもらう」「助け合う」関係が自然に生まれます。ぜひ、できることから始めてみてくださいね。
まとめ|小さな備えが大きな安心に
杖やステッキは、毎日の生活を支える大切な相棒。
その相棒とともに、災害時も安心して過ごせるように、今できることを少しずつ整えていきましょう。
無理なく、できることからで大丈夫です。
ご自身のため、大切なご家族のために、ぜひ「災害時の備え」を見直してみてくださいね。