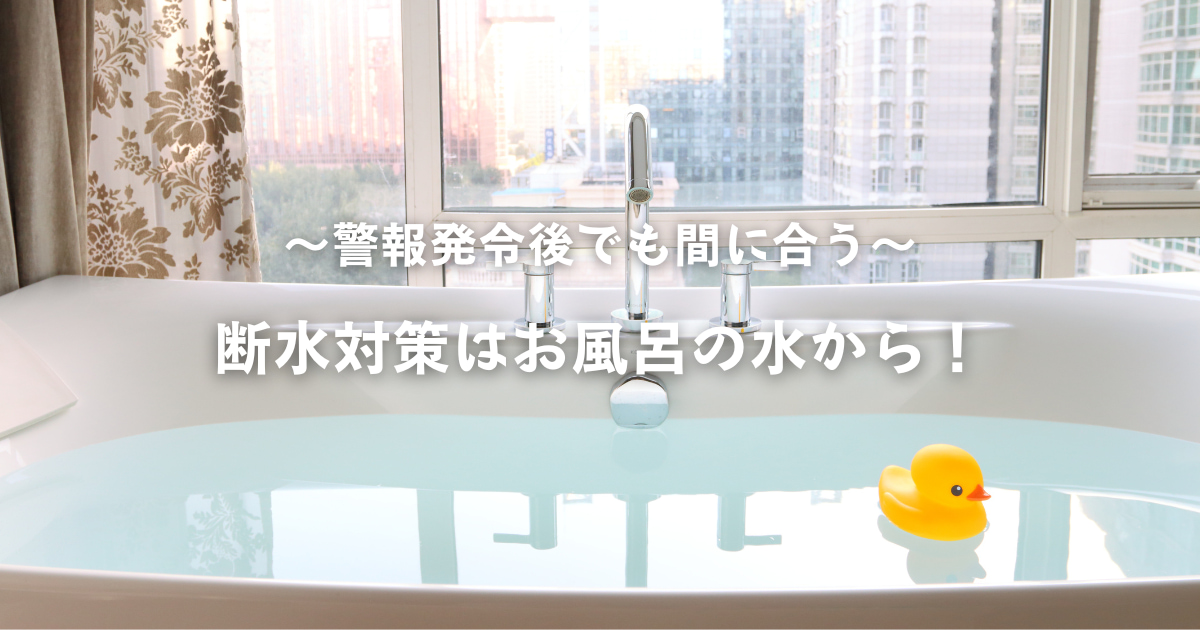7月に入り、いよいよ台風や梅雨の影響で大雨が増える季節になってきました。
実は、地震や火災と並ぶ自然災害の中でも、「水の災害」は夏にこそ多く発生しています。
その中でも特に気をつけたいのが、「洪水」による被害です。
河川の氾濫、用水路のあふれ、都市部での内水氾濫…。
近年では「まさか自分の町が」という場所での被災も増えています。
でも、洪水はある程度“前ぶれ”がある災害。
だからこそ、その“前”の段階で「何を見て」「どう判断して」「どこへ避難するか」を知っておくことが、命を守る大きなカギになります。
今回は、洪水に備えるための防災情報や、避難のタイミング、実際の行動のコツを、まとめてご紹介します。
洪水の原因とリスクを知ろう

洪水といっても、いろいろなタイプがあります。
まずは「どんな風に起きるのか」「自分の地域にはどのリスクがあるのか」を知っておくことが大切です。
河川の氾濫(外水氾濫)
大雨により川があふれ、堤防を越えて水が広がる現象。
川の近くや低い土地、田んぼの多い地域で起きやすいです。
内水氾濫
都市部でよく起きるタイプ。
排水が追いつかず、道路や住宅地に水がたまってしまう現象です。
地下や低地の浸水
地下街や地下鉄、半地下の店舗や駐車場などに水が流れ込みやすく、
命の危険につながるケースもあります。
「川が近くにないから安心」ではなく、
自分の住む場所にどんな洪水リスクがあるのか、ハザードマップで確認しておくことが何より大切です。
洪水時に注意したい「避難のタイミング」

洪水は、水があふれてからの避難では遅いことが多い災害です。
特に、以下のタイミングではすでに避難が危険な場合もあります。
- 周囲が冠水し始めている
- 川の水が道路と同じ高さになってきた
- 夜間で視界が悪い/雨風が強い
では、どんなときに避難を判断すればいいのでしょう?
▶ キーワードは「警戒レベル」
災害時、自治体からは「警戒レベル」で避難の呼びかけがあります。
- 警戒レベル3:高齢者等は避難開始
- 警戒レベル4:全員避難
- 警戒レベル5:すでに災害が発生中(命を守る行動を!)
つまり、「警戒レベル4」が出たときには家族みんなが避難を始めるべきタイミング。
その前に、「どこに避難するか」「どうやって移動するか」を決めておくのが理想です。
家族で話す「3つの避難の準備」

避難といっても、ただ避難所に行けばいい…というわけではありません。
事前に、次の3つの準備を家族で共有しておくと、いざという時に慌てずにすみます。
✅避難先の候補を2つ以上
- 公共の避難所(学校・公民館など)
- 安全な友人・親戚宅(できれば標高の高いエリア)
- 車での避難はできる?周辺に高台はある?
特に小さなお子さんや高齢の方がいる場合は、「静かに過ごせる場所」も大事な視点です。
✅避難ルートを実際に歩いてみる
- 冠水しやすい道はないか
- 坂道・階段・暗い道が多くないか
- 雨の日にベビーカーや車椅子で動けるか
スマホの地図ではわからない“リアルな道の状態”は、実際に歩くことでしか見えてきません。
✅持ち出し袋の再点検(特に水災害用)
- タオル類・レインコート(傘は使いづらい)
- 防水仕様の袋やケース(スマホや貴重品を守る)
- 懐中電灯(電池のチェックも忘れずに)
- ゴミ袋やジップ袋(濡れた衣類の仕分けなどに)
「濡れたら困るもの」を守るという視点で、持ち物を見直しておきましょう。
洪水後にも気をつけたいこと
実は、洪水が収まった後にも注意すべきポイントがあります。
- 床下・壁のカビや衛生被害(早めの清掃・換気)
- 感電の危険(ブレーカーは必ず切る)
- 偽の修理業者・義援金詐欺などの二次被害
災害の直後は気が動転しがちですが、「落ち着いて確かな情報を選ぶ」ことが自分と家族を守ります。
まとめ
洪水は、夏にこそ身近になる災害のひとつです。
でも、きちんと準備しておけば、命を守る行動がとれます。
- ハザードマップを見て、地域のリスクを知る
- 警報や警戒レベルに注意する
- 避難のタイミングを家族で話し合う
- 雨の日を想定した防災グッズをそろえる
どれも、今日からできる「小さなそなえ」です。
大げさなことではなくても、“今ある暮らし”の中に、防災の視点を少し加えるだけで、未来が変わります。