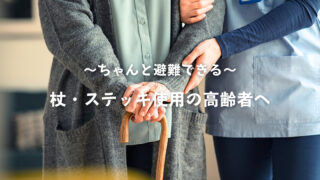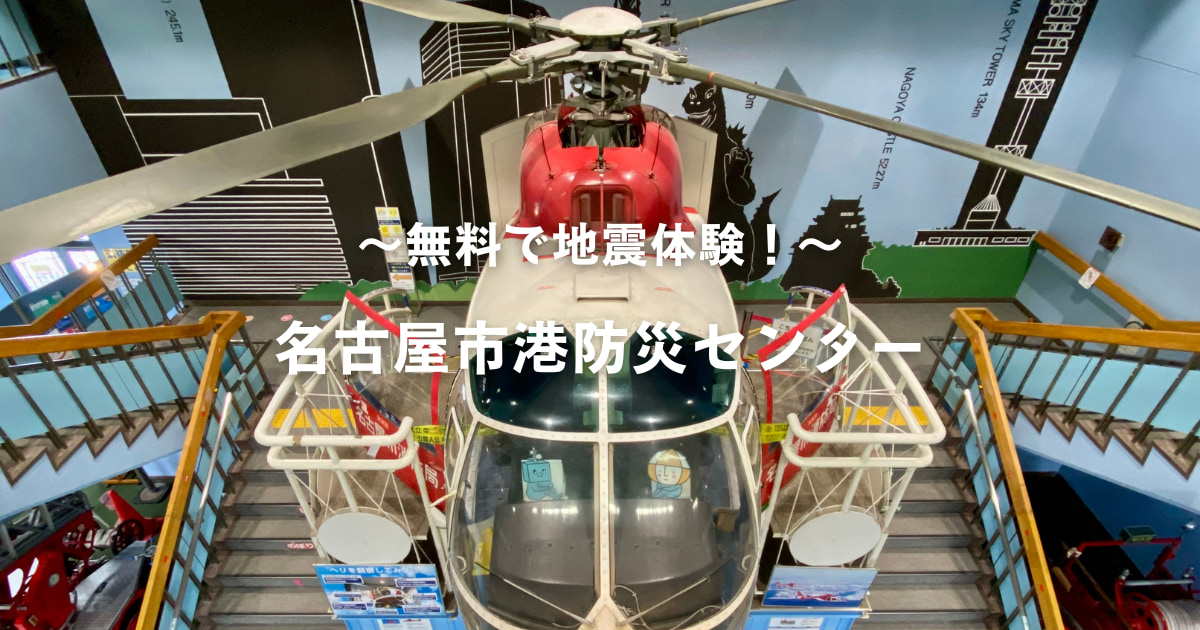「防災ボトル」ご存じですか?
これは、警視庁警備部防災対策課がX(旧Twitter)で紹介し、約6万いいねを集めたアイデアです。1本のウォーターボトルに「最低限の備え」を詰め込み、外出時にも手軽に防災対策ができると話題に。
災害情報が頻繁に聞かれる今、シニア(高齢者)世代にもおすすめしたい携帯備蓄の形として注目されていますので、是非準備してくださいね。
我が家もそれぞれ自分の防災ボトルを作りましたよ!
防災ボトルとは?

外出中の災害発生に備えて、必要最低限の防災グッズをウォーターボトルにまとめて持ち歩くという防災対策のひとつです。
バッグやリュックに入れてもかさばらず、いつでもどこでも持ち運べるのが魅力です。
防災ボトルの本質的なポイント
1.コンパクトで持ち運びやすい
ウォーターボトルはスリムで軽量。外出時のバッグにも収まりやすく、気軽に携帯できます。
2.水に強い
多くのボトルは防水性があり、雨や水害時にも中身が濡れるリスクが少なく安心です。
3.中身が潰れにくい
ポーチや袋よりも硬い素材のため、内容物をしっかり保護できます。
4.すぐに取り出せる
必要なものをひとまとめにしておくことで、緊急時に慌てずスムーズに対応可能です。
5.給水ボトルとして再利用可能
中身を出せば、水を入れるボトルやコップとしても活用できます。
自分仕様にカスタマイズを
防災ボトルは、一人ひとりの生活スタイルや体調に合わせて中身を工夫することが大切です。
例えば、乳幼児がいる人はベビー用品、高齢者は常備薬など、状況に応じたアイテムを選びましょう。
100円均一のダイソーや無印良品などでは、防災ボトルに適したシンプルで機能的なウォーターボトルや携帯グッズが豊富にそろっています。市販のキットも参考にしながら、自分に合ったセットを作ってみましょう。
防災ボトルってどうやって作るの?

ステップ①
まずはベースとなるボトルを用意します。
・容量は500ml程度で、透明なプラスチック製が◎
・取っ手やフタが大きめで扱いやすいものがあると便利
・水に強くて中身も潰れにくいという点もポイントです
ステップ②
・パッケージ包装紙から出せるものは全部出す
➡空気を抜いて中の量をコントロールしやすくします
ステップ③
・薄いものから詰めて壁面を整える
➡マスクやビニール袋などを側面に沿わせると真ん中に空間ができます
ステップ④
・重めのもの・取り出したいものを上に配置
➡ミニライトやホイッスルがすぐ手にとれる配慮も◎
シニア向け防災ボトルの「中身」、これだけは入れておきたい!
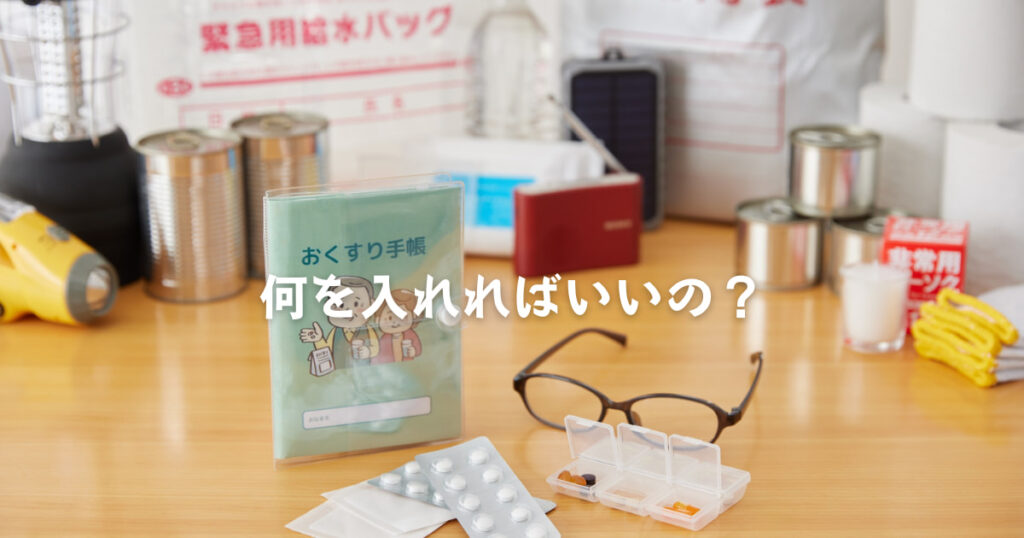
高齢者(シニア)世代の方にとっても、「防災ボトル」は、外出や災害時の強い味方になります。
中身はしっかり考えてみましょう。
| アイテム | 理由 |
|---|---|
| 圧縮タオル+ウェットティッシュ | 手洗いやけが対応にすぐ使える |
| 絆創膏・常備薬 | 服用済みか貼り忘れが一目で分かるよう、まとめておくと安心 |
| 補聴器電池・お薬手帳コピー | 聴覚や持病のある方 |
| ミニLEDライト | 停電や夜道での足元照らしに有効 |
| ホイッスル | 緊急時の助け合いに。小さくて音も力強い |
| 飲料ゼリー・飴等 | 噛まず飲めて、高齢者でも取りやすい |
| 現金(1,000円札やコイン) | ATMが使えない場合も対応可能 |
| 連絡先メモ | 「お薬・連絡先・アレルギー情報」などメモに |
| 防水ラベル、名札 | 自分用と分かりやすい表示に |
*冬の時期には、防寒対策グッズも高齢者には欠かせません。軽くて保温性の高いアルミ製シートや使い捨てカイロを入れておくことで、体温低下を防げます(季節によって見直しもしてみてください)。
こうして防災ボトルを用意しておけば、転倒・急変・情報不足・寒さといったリスクを、ボトル1本でしっかり支えられるようになります。高齢世代の備えにも、ぜひ取り入れてみてくださいね。
家族で楽しむ“防災ボトル”アレンジガイド

災害はいつ起こるか分からないから、家族みんなで対策を楽しく共有することが鍵。警視庁が公式Xで紹介した「防災ボトル」をベースに、小学生・大人・高齢者向けにアレンジするだけで、お出かけにも安心感が増します。
我が家でも、ボトルの色を変えて誰の分か一目でわかるように作ってあります!
👧 小学生バージョン:学校外でも安心!
- 内容:圧縮タオル、キッズ絆創膏、ホイッスル、マスク、飴、連絡先メモ
- 使い方:
- マスクやティッシュは外で使いやすい
- ホイッスルは首からかけて、もしも声が出せなくても安心
- 飴や飴菓子はエネルギー源にもなる嬉しいアイテム
- ポイント:ラベルやカラーを子どもに選ばせると、「自分のボトル」という愛着がわいて自然に防災意識が育ちます。
👩💼 大人バージョン:通勤や習い事にも無理なく携帯
- 内容:ミニ懐中電灯、携帯充電ケーブル、防災ポンチョ、アルミブランケット、常備薬、現金
- 使い方:
- 夜の帰宅でもライト一つで安全に
- ケーブルは災害時のスマホ充電に備えて
- お札や硬貨はATMが使えない緊急時の備え
- ポイント:軽量アイテムだけでバランスよく。常に持ち歩いても負担になりません。
👵 シニアバージョン:安心できる「手元備え」
- 内容:圧縮タオル、常備薬、お薬手帳コピー、補聴器用電池、ミニLEDライト、ホイッスル、飴、現金・連絡先メモ
- 使い方:
- 水没対応のラベルや大きめ文字で見やすさを優先
- 飴など食べ慣れたもの、すぐ栄養補給可能
- 電池やホイッスルはいざという時に心強い味方
- ポイント:持ち物の名前を記入してもらい、本人でも自信をもって使える配慮を。
まとめ
自宅やおでかけ先で、家族それぞれの防災ボトルをお揃いでつくるのも一案。色やシールで個性を出すだけで、家族会議がもっと楽しく、防災が「しんどい課題」ではなく「いっしょに育てる習慣」に変わります。