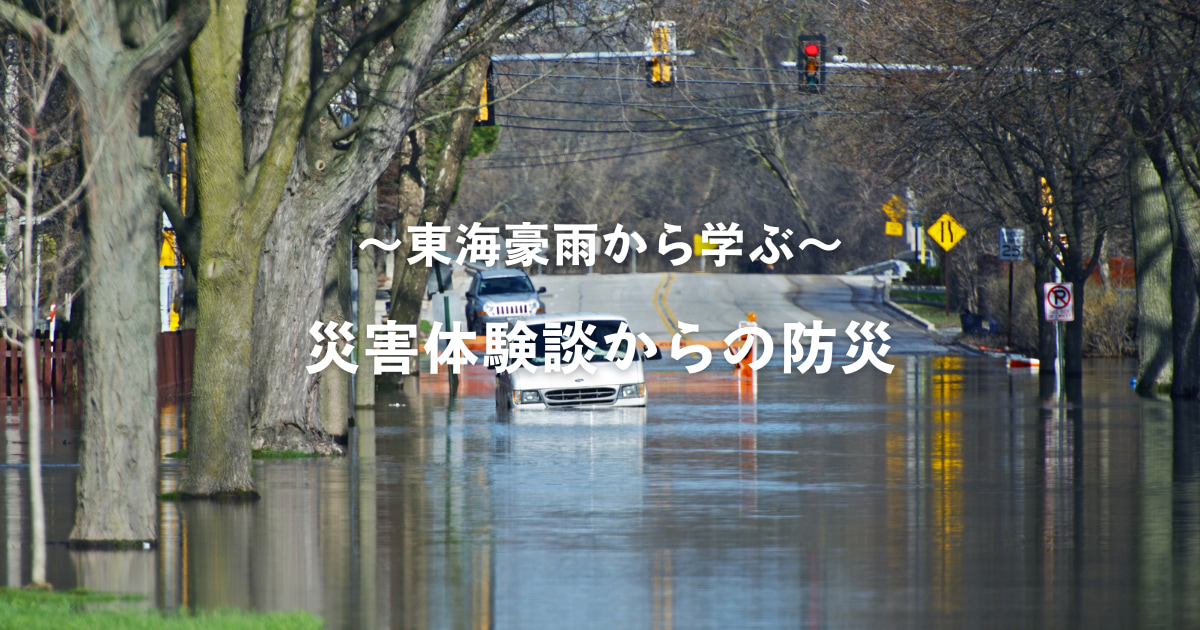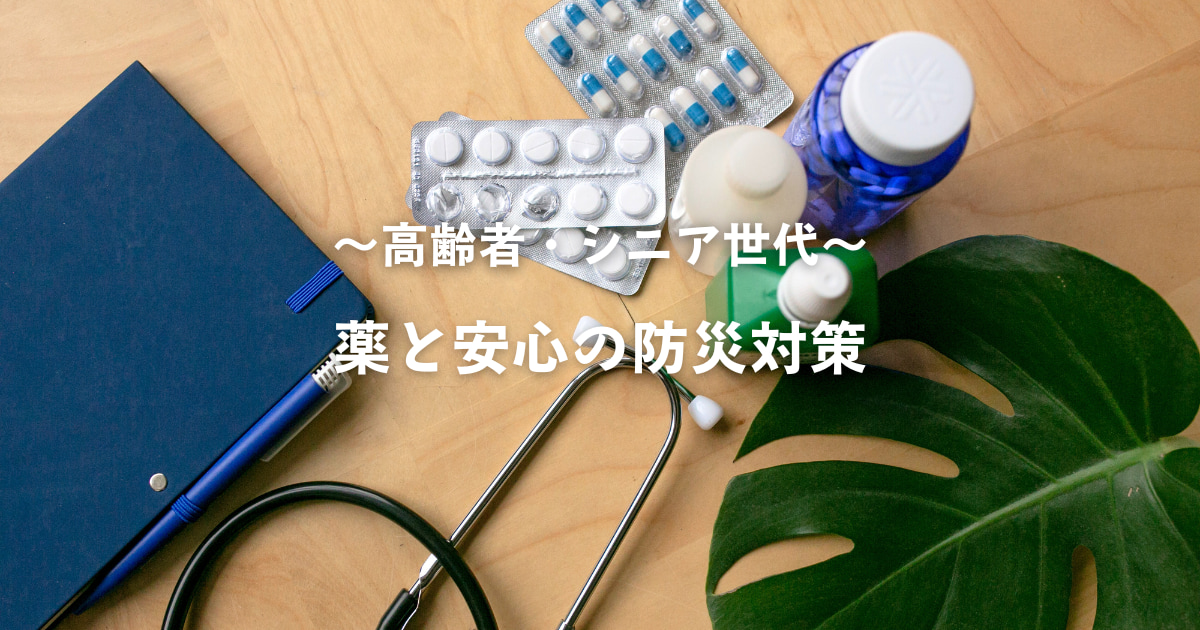「まさか、こんなことになるなんて…」そう思うような災害が、ある日突然やってきます。
2000年に起きた東海豪雨は、まさにその“まさか”を現実にした出来事でした。
名古屋市やその周辺を襲った記録的な大雨。道路や住宅が浸水し、たくさんの方が避難を余儀なくされました。私も愛知県に住んでいるので、あのときの出来事は決して他人ごとではなく、今も忘れられません。
今回は、東海豪雨の体験談をもとに、「私たちが今、どんな備えをしておけばいいのか」を、お伝えします。
東海豪雨とは?いつ、どこで?
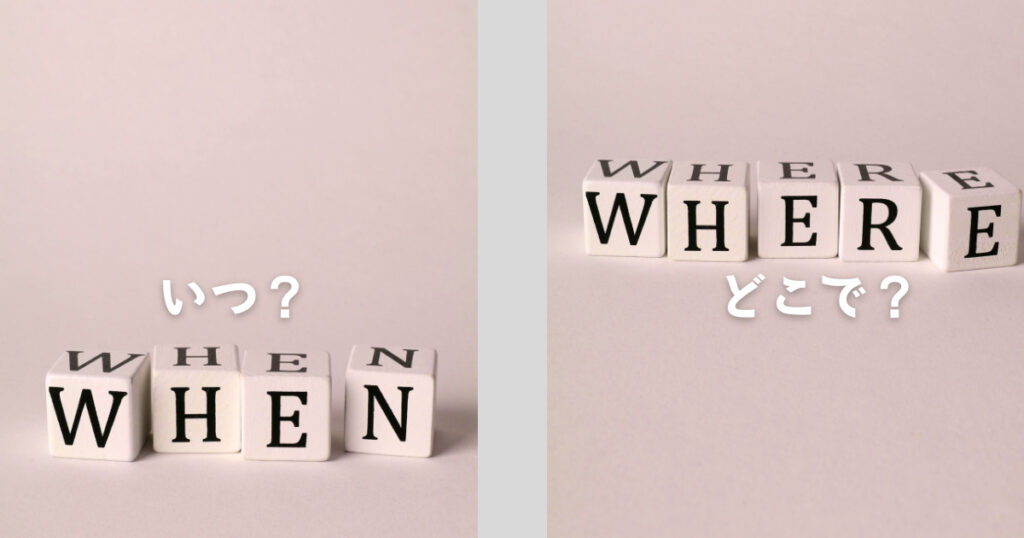
東海豪雨は、2000年9月11日から12日にかけて発生しました。たった1日で、名古屋市を中心に400ミリ以上もの雨が降り、新川が破堤、多くの河川が氾濫。名古屋市内では約30,000戸が床上・床下浸水するなど、大きな被害が出ました。
当時、ナゴヤドーム浸水、地下鉄の駅や地下街にも水が流れ込み、車が水没したり、自宅から出られなくなった方もたくさんいました。特に印象的だったのは、「あっという間に水かさが増え、逃げる時間がほとんどなかった」という声です。
こうした大雨災害は、決して昔の話ではありません。
実体験談から「備えていてよかったこと」

東海豪雨を経験された方々の声を聞くと、「これがあって助かった」「準備しておいてよかった」というリアルな気づきがたくさんあります。
・停電にそなえ、懐中電灯や電池を用意していた
・飲料水や非常食を少し多めにストックしていた
・事前に避難場所を確認したおかけで、スムーズに避難できた
・車を高台に移動していた
・家族で「どうするか」を話しあっていた
ある方は、「玄関先に土のうを積んでいたおかげで、浸水を最小限に抑えられた」と話していました。また、地域の人たちが声を掛け合い、助け合ったことで、被害を減らせたケースも多かったようです。
「これがなくて困った…」反省と気づき

準備が足りずに困ったという声も多く聞かれました。
・ライトの電池が切れていた、スマホの充電ができなかった
・水や食料が足りなかった
・車が水没した
・断水でお風呂に入れなかった
・自治体からの情報不足で、判断が遅れた
特に「情報が遅れた」「判断が難しかった」という声は、今の私たちにとっても重要な教訓です。
災害時は、テレビやスマホの情報だけでなく、地域のハザードマップや避難情報アプリ、ラジオなど、さまざまな情報源を準備しておくことが大切です。
東海豪雨の教訓から考える

大きな災害を経験した地域だからこそ、できることがあります。完璧じゃなくてもかまわない、ちょっとずつ、できる範囲で備えていきましょう。
✔ 普段の生活にプラスする備え
- 買い物のついでに、水や食料を少し多めにストック
- 懐中電灯やモバイルバッテリーのチェック
- 家族で避難場所や連絡方法を確認しておく
✔ 家や地域のリスクを知る
- ハザードマップで浸水の危険エリアを確認
- 自宅の排水溝や側溝を定期的に掃除
- 必要なら止水板や土のうを準備
✔ 判断力をつける情報収集
- 防災アプリやSNSを活用する
- 気象情報や避難情報を日ごろからチェックする
- 地域の防災訓練に参加する
「ちょっとやりすぎかな?」と思うくらいが、ちょうどいいのかもしれませんね。
まとめ
東海豪雨は、多くの人に「災害は突然やってくる」「備えが自分や家族を守る」ことを教えてくれました。あの経験を無駄にしないためにも、できることを少しずつ積み重ねていく必要があります。
「全部やろう」と思うと疲れてしまいますが、
- いつもの買い物で備蓄を少しプラスする
- 家の周りの危険を見直す
- 家族会議をしてみる
そんな小さなことから始めていけば、きっと安心につながります。私自身も、日々の暮らしに“少しづつい防災”を取り入れています。